読書をするのはとても素晴らしい事ですし、一般的に読書が好きな子の成績は、高い傾向にあるのもまた事実です。
読書の効用は、脳に様々な良い影響を与え、集中力がつき…、と、他にも数えきれないくらい大きなものがあります。
なので、もちろん出来れば、読書はして欲しいのですが、また一方で、「試験の文章になると読書のようにはいかない。」「読書をしているのに国語の成績に結びついていない」…などという事も、あり得ない話ではありません。
読書ですとスラスラと速いスピードで楽しんで読めているのに、試験の文章になると急にゆっくりと大変な思いをして読んでいる、読みづらくなってしまう、という事もあり得ます。
もちろん読書は「読みたい本」を読めば良いのに対し、試験はそういう訳にはいかないという事情もあるかもしれません。
しかし、実はそれ以上に、根本的な原因があるのです。
たとえ同じ文章だったとしても、「読書」と「試験」では、大きな違いがあります。
またそれを知っておく事は、国語の勉強をする上において、とても役に立つ事になります。
試験の文章は「切り取り」であるという事。
もちろん国語の試験において、本を丸ごと一冊読ませる事は出来ません。
つまり本のどこかの部分を「切り取った形」で出題されます。(出題者がオリジナルで書いた短い文章や新聞のエッセイなどは除きます。)
当たり前の事ですが、この違いは大きなものがありますし、これによって試験ならではの様々な難しさが出てきます。
読書が「連続ドラマ」を観るようなものだとするならば、試験に出てくる文章は「映画」を観るみたいなものと言えるかもしれません。
いきなり途中から話が始まるので、時間をかけずになるべく早い段階で、物語文であれば話のシチュエーション、説明的文章であれば何について話しているのかなど、把握出来ないとなりません。
映画でもしばらく観ていないと慣れるのに苦労したりするのと同じく、国語の試験問題もいつも慣れていないと、この力が弱くなってしまい苦労します。(入試が近づいてきた時に、国語の成績は良いから…、とあまりやらないでいると、急に出来なくなってしまう原因の一つです。)
読書をする事は、国語の「根本的な力」をつけるのにとても役には立ちますが、試験用の文章は「別物」として慣れていかないと、なかなか出来るようにはならないという訳です。
物語文において。
作問者は本文を選ぶ際、普通はまず大問のテーマとして使いたい、一番盛り上がるところ(クライマックス)を決め、そこに関係する所を切り取ります。
そうすると、どういう事が起こるでしょうか?
大抵の場合、中学受験の物語文のパターンである「−(マイナス)→きっかけとなる出来事→+(プラス)」という形が出てきます。(ちなみにココに主題(テーマ)が出てきます。)
例えば「口うるさい親の事をうっとおしいと思い避けていた(−)→たまたま親が自分の事を深く考えている事を実感するような場面を目撃してしまう(きっかけ)→親の愛情に気づき、見る目や接し方が変わる(+)」みたいな…。(ちなみに−から+がほとんどで、逆はほとんど見かけません。さらに「成長」に関するものが多いです。)
中学受験の物語文はこのパターンが多いのですが、理由もなくそうなっている訳ではないのです。
この「本文の『主題(テーマ)』が分からないとあるレベル以上の問題は解けないですし、しっかりと理解しておかなくてはならない大事なポイントです。
ただ大事なのは、その「主題(テーマ)」というのは、その本を書いた作者のもの(本全体を通してのもの)というよりは、作問者が選んだもの(その大問の中での中でのもの)と言う所です。
ここから、読む方はこれを逆手に取って、「試験としての読み方」みたいなものが出てきます。
つまり余計な所は本文に入れていないはずなので、型を意識して読めば、大まかに速く正確に内容をつかむ事が可能なのです。
またそういう事を意識して読まないと、短時間であんな長文をサッと読んで内容を把握するような事は、厳しいかもしれません。
あと読書と違って「切り取り」ですので、前置きの部分ををしっかり読んだり状況を把握したりなど、いくつか注意するポイントや、やらなくてはならない事が出てきます。
ちなみに、この大問の中での主題(テーマ)が分かっていないと、あるレベル以上の問題は解けませんし、当然入試や模試の中にも出てきます。
説明的文章において。
論説文など説明的文章でも、ある本からの「切り抜き」であるという点は同じですし、関係ない所は入れないというのも同じです。
その結果、「話題→本論→結論」みたいなパターンになるのも当然と言えば当然です。
元々そのように使う所を選んで、切り取っているものなので…。
読む方としては、なるべく早い段階で作者の言いたい内容の方向性がつかめれば、より速く正確に読める事になります。
そのために話題をつかんだり、意見と例を分けて対応させたり、問いかけ→答えに注目したり、対比構造に気付いたり…など、いくつかやるべき事はありますが、それが出来る(やりやすい)のも、全て「関係あるカタマリの部分だけを切り取ってあるから」こそです。
読書も一章ごと単元ごとなどで、まとまりがあるとも言えますが、試験に出されるものはなお一層、カチッと一つの構造物のようにまとまってとらえる事が可能です。
逆に言えば、それが出来ないと試験においては結構苦労しますし、「切り取り」ゆえの性質を利用して、「読み方」の技術を覚えて使えるようになれれば、楽に読む事も可能になってきます。
読書をするという場合、大抵は小説みたいなものを指す事が多いと思いますし、物語文と試験の文章の違いによって、苦労している方の方が多いかもしれません。
しかし、やはり説明的文章においても、一般的な読書と試験の文章には違いがあるという事です。
まとめ
読書をしているのに、試験の文章になると急に読みづらくなってしまう原因について書きました。
試験は一部を切り取ったものなので、読書する時と全く同じようにはいかないというお話でした。
でもこれは逆にチャンスにもなり得ます。
決まったルールの中で戦うからこそ、読み方のような、テクニックみたいなものが生まれてきますし、もしそれを使えるようになれば有利にもなります。
もし読書が好きな生徒さんが、そういう論理的な読み方まで身につけたら、まさに「鬼に金棒」となる事でしょう。
もし、「読書は出来る、活字を読むのは苦痛ではないのに、試験になると急に読めなくなる」みたいな方がいらっましゃいましたら、是非この事を頭に入れて、試験の文章ならではの「読み方」の方も学んでいってもらえたら、と思います。

-300x269.png)


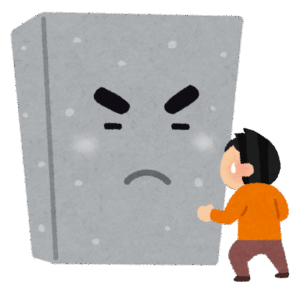




コメント