記述問題を全く書けない人は、また別の問題がありますが、そうではなくて…。
「近いのは書けるんだけど、いつも△をつけられ何点か減点されてしまう。」
「模範解答と比べてみても、どこで点数を引かれているのか今ひとつ分からない。」
「そもそもどんな風に採点しているのか。」
などなど、書けない訳ではないけれども、いつも点数を引かれてしまう人がいます。
全く違う事を書いているとかいうのであれば、×になりますので分かりやすいのですが、いつも模範解答と似ている気がするのに、点数を引かれてしまうような人です。
記述問題で満点が取れる時。
まず「どういう時に記述で満点がもらえるのか?」をしっかりと知っておく事が大切です。
それが分かれば「なぜ点数を引かれているのか?」も分かりますし、「どういう答案を作れば良いのか?」も分かります。
それは、一言で言ってしまえば、「作問者の問題を出す『意図』を理解して、その『要求』を満たした時」です。
記述の採点ポイントを決めるのは作問者。
問題を出す時というのは、他の科目と同じく、その問題を解く人の「ある力」を試す目的で出します。
つまり「ある力」を試しているのに、それが書かれていなければ、点数はあげられないのは当然です。
問題を出題した作問者の「意図」とも言えます。
(本番の入試では、これを発表している学校もありますので、そういう学校を受験される方は、もちろん入手した方が良いです。)
話を分かりやすくするために、いくつかの簡単な例を見てみましょう。
「予習シリーズ6年上(第2回発展問題 問1)」より
主人公が「自分の席に戻ったのはなぜですか?」と問う問題です。
傍線部の前を見ると、いわゆる「自分の世界」を持った女の子が一人で食事をしている姿が見えた様子が書いてあります。
「その顔を見た瞬間〜」とあるので、明らかにその彼女を見た事が原因です。
でも、答案にその事を書いても、というか書いただけでは、大きく減点されてしまいます。
なぜなら、物語文において「行動の理由」を聞かれる場合、その原因となる「心情」が分かっているかどうかを試すという「意図」で出題されるからです。
なのできちんと、「彼女を見た事によって、自分も無理して周りに合わせるのが耐えられなくなったから。」と「気持ち(心情)」を入れないと、点数に結びつきません。
(もちろんこの通りに答えなくても、「馬鹿らしくなったから」「いやになったから」「つらくなったから」・・・など、方向性が同じなら大丈夫です。)
この問題だけではなく、物語文で「なぜ?」と聞かれたら、作問者が「心情」が分かっているか試したいので「心情」で答えないとなりません。
ものすごく初歩的な所ですが、こんな事でも知らないと、たとえ内容的には間違っていなくとも、大きな減点の対象になってしまいます。
「物語文で『行動の理由』を聞かれたら『(理由)+(気持ち)で答える』」です。
「女子学院中(2024年度)大問1 問3」より
「手作りのステンドグラス」に傍線が引かれていて、「何のどのような様子を表現しているか、説明しなさい」という問題です。
もちろん「何の、どのような様子」か聞かれているので、その形で、そのまま答案に書かないとなりませんが、まずすでにココの時点で、怪しい答えが出始めてきてしまいます。
とにかく作問者の意図は問題文に出てくるので、そこを徹底的に見るのは大原則です。
それからこの問題の意図ですが、「『比喩』が分かっているかどうか試したい」という事です。
それを意識して、答案に表現しないといけません。
それでもまだ問題文に「表現」という語句が入っていますので、分かりやすく丁寧に聞いてくれている方です。
(ちなみに抜き出し問題とかでも、作問者がわざわざ問題文に「〜表現」と書いてくれているのに、そんな事は関係なく時間をかけて、何の見当もつけずに探している人なんかも、よく見受けられます。)
さて、この場合、まず「手作りの」を説明しないとなりません。
田舎の村里にある古い田んぼで、手作りの感じは何となく分かっても、説明するとなると難しいかもしれませんが、よく見ると傍線部近くに「区画が入り組んで」とか使える所もあったりします。
また「ステンドグラス」も難しいかもしれませんが(まず知ってるかどうかの問題もありますが)、同じく傍線部近くの本文中に「一つ一つの田が、それぞれの色合いを湛えて〜」などと便利に使えそうな所もあったりします。
それで「区画は入り組んでふぞろいだが、田んぼの一枚一枚が(=一つ一つの田が)それぞれの色合いの水を湛えている様子。」みたいな解答が、あまり時間をかけずに書けてしまいます。
もし説明する言葉を全て自分で作らなくてはならないような問題だとしても、「比喩を直す」という作問者の出題の意図をキチンと意識出来てるかどうかは大きな差をつけます。
(そうでないと何となく漠然とした答え、または間違った答えになってしまいます。)
この問題の場合、「手作りの」とは「ステンドグラス」とは、どんな様子か書けていないと点数はもらえません。
(一見簡単そうに見えるかもしれませんが、作問の意図が分かっていないと、きちんと満点にならない事もありますし、実際多いです。)
「比喩表現の問題は、『傍線部を分けて、それぞれを言い換える』」です。
まとめ
簡単な例をいくつか見ただけですが、問題を作った人の「意図」に対して答えられているかどうかで点数をつけるのが、記述問題です。
客観的に合っているかいないか、というよりは、要求されたものが入っているかいないか、という感じです。
なので、「こう聞かれた時はこういう意図で出されている」といういくつかのパターンを覚えて、それに応じて答えられるようにする事が必要です。
是非そういう観点から、記述問題の模範解答と自分の答えを比べてみてください。
なぜ点数を引かれてしまっているのか、またどうしたら点数がアップするのか、という事が見えてくると思います。
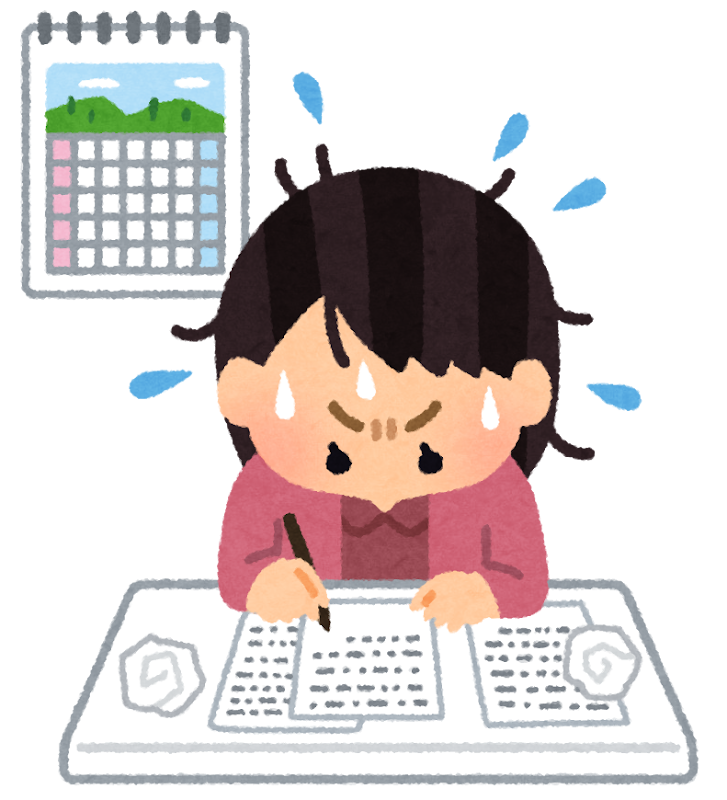
-300x269.png)


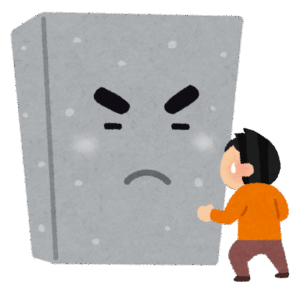




コメント